
 |
← 左のタイトルを選択してクリックしてください! 教授 高山 勝己 (Professor, Katsumi Takayama, D. Agrl.)メールアドレス: takayama●fukui-nct.ac.jp (●を@に変えて下さい)・ 経歴・業績については、 Go to Researchmap このホームページは在学生並びに中・高生の方(保護者)を対象として作成しています。  福井高専と同じ59歳です。 ご挨拶 はやいもので福井高専に着任して30年をこえました。 この間いろいろな人と出会いお世話になってきました。 時には厳しい叱責を受けたこともありました。しばらく立ち直れなくなったその時の経験が今の自分をつくっています。本当に感謝です。 あれがないこれがないと不満を覚えた時期もありましたが、与えられた環境の中で何ができるのか?自分はどのようにしたら社会に貢献できるか模索してきました。地域の方がいろんな問題を相談に研究室を訪問してくださいます。むしろ専門外のことの方が多いのですが、出会いを大切にし、一緒に考えてみることで解決の糸口が得られると信じています。 主に微生物を用いたバイオセンサー、バイオリファイナリー、環境浄化に関する研究を行っています。最近は食品や農業に興味を持っています。その一つとして土壌微生物の評価法に取り組んでいます。 常に謙遜であることを、そして3C(Compassion, Conviction, Communication)の賜物が与えられるよう日々願っています。高専に入学してくる学生さんが“夢”を持てるような教育・研究指導ができればと思っています。 座右の銘: まだまだ至りませんが、〝克己復礼” です。 Profile Katsumi TAKAYAMA received the BS degree in material science from Toyohashi University of Technology in 1988, and obtained the PhD degree in agricultural chemistry from Kyoto University in 1997. After working as a Research Assistant and Associate Professor, he has been serving as a Professor in the Department of Chemistry and Biology of Fukui National College of Technology. His current research interest is development of biosensor and bioremediation. 好きな名言 I was like a boy playing on the sea-shore, and diverting myself in now and then finding a smoother pebble or a prettier shell than ordinary, whilst the great ocean of truth lay all undiscovered. Isaac Newton 偉大なる人物!ニュートンであるがゆえの言葉。なんと高尚なことか! 研究室の変遷 当研究室の原点は、創立時工業化学科・初代高岡和則先生に始まります。高岡先生は、ポーラログラフィーに関する研究で学位を取得され、福井高専在職期間中、一貫してポーラログラフィーでの研究を行われました(電気分析化学研究室)。30年以上にわたり、時流に惑わされることなく研究テーマに一貫性を持たれていたことは私にとって驚きでありました。時が流れ、環境問題から水銀の使用が厳しくなったことで、最後の数年間は研究方針の変更を余儀なくされました。かつて実験室では水銀精製装置が連日夜中まで稼働し、先生がカロメル電極や様々な機材を自作されていた姿が懐かしく思われます。その実験室の傍らに机を置いていた私には、水銀の中で生活しているようで少々不安な気持ちだったのですが現在も健康であるところを見ると大丈夫なようです。柳本製作所の初代タイプの測定装置を手を加えながら大切に退官のときまで愛用されていました。私も短期間でしたが借用させていただいたこともあり、ご退官のときに廃棄を余儀なくされましたが、今思えばかなりのレアもので記念に保管しておけばよかったなと後悔しています。担当教科は物理化学であり教育にとても熱心で、講義に備え毎日勉強に励まれていました。学生からの質問に、どんなに多忙であっても真摯に対応されていました。そして“教育者たるもの日々の日進月歩にありますよ。向上心を失ったのであれば学生に害を及ぼすだけでもう教師はやめるべきですよ”といつもおっしゃっていました。 2代目は吉村忠与志先生。化学工学を専攻され、同じくボルタンメトリー分野でのご研究で学位を取得され、後にコンピューターケミストリーの研究に転換され、さらに化学教育の分野で多大なる貢献をされました。関連の学協会の設立にも尽力されました。多忙な中、地域の問題にも積極的に関心を寄せられ、多くの環境科学に関する研究課題に取り組まれました(地球環境化学研究室へ改称)。私も幾つかのテーマを一緒に取り組ませていただき楽しませていただきました。また小中学校への出前講座に早くから取り組まれ、地域社会の相談役としても積極的に対応されていました。この間、学科名称が工業化学科から物質工学科へ改組となり専攻科も設置されました。 高専の教員とはいかにあるべきか?という私の大きな疑問に1つの答えを与えてくださった先生であります。 このように歴代2人の先生のもとで得た経験は、高専の教員としての自身の教育・研究哲学を形成するために大きな礎になりました。そして微生物を利用した研究に重きを置く研究室(応用微生物学研究室へ改称)として現在に至っています。 隔月 今年のノーベル賞! 今年は2名の日本人がノーベル賞を受賞した。生理学・医学賞の坂口志文先生と化学賞の北川進先生のお二人だ。わが物質工学科に関係するのは北川先生のご研究だろう。北川先生の研究は、PCP/MOF(Porous
Coordination Polymer/Metal-Organic Frameworks)と称する結晶構造を有する固体の多孔性材料(金属イオンと有機分子で構成される多孔性配位高分子)の創製であり、よく知られたゼオライトのような無機物ではなく、金属と有機分子から構成される材料*ということがポイントといえる。 PCP/MOFを用いた技術はいくつか発表されているようだが、例えばCubiTanR(Atomis社プロデュースの次世代高圧ガスボンベ)という製品がある。一般的な150気圧高圧ガスボンベは大人の体重程度(60kgくらい)あり、私の実験室では同サイズのN2、Ar、CO2ボンベを使用しているが、交換のたびに一苦労している。CubiTanは1/6程度まで重量を軽量化できるというから普及が待ち遠しい。 体育祭 9月25日恒例の体育祭が開催された。残念ながら天候に恵まれず、午後からは体育館に移動しての実施となった。わが担任のクラスは、物質工学科のリーダーとして応援にデコレに奮闘していた。応援団長をはじめみんな活き活きとしていた。若さはすばらしい!残念ながら入賞することはできなかったが、全力を尽くした結果なのだから悔いはないだろう。“これが4年担任として最後の体育祭になるなー”と、ふと考えがよぎった瞬間、目頭が熱くなった。 時の過ぎるのは早く、担任業務自体もいよいよ後半戦にはいる。悔いのないようしっかりやっていきたい!  すばらしかったです!担任としてはNo.1!  全員集合???といいたいところだったんですが 石堂ゆみ先生 講演会開催しました! 7月24日(木)4Cホームルームの時間に、ジャーナリストである石堂ゆみ先生にお越しいただき、ナチスによるユダヤ人迫害の歴史についての講演を行って頂いた。 石堂先生はイスラエルに長く滞在された経験を持たれ、日本人初のヤド・バシェム(イスラエルにあるホロコースト記念館)公式日本語ガイドをつとめられている。 先生のお話の内容を、ここに記述したいところであるが長くなるので、ホロコーストの事実を記した書籍をまだ一度も読んだことのない学生さんは、これを機にぜひ読んでほしい(高山が一読を薦めるベストセラー3冊は:1)私はガス室の「特殊任務」をしていた,シュロモ・ヴェネツィア著,河出書房新社、2)夜,エリ・ヴィーゼル著,みすず書房、夜と霧,ビィクトール・E・フランクル著,みすず書房であり、どれを読んでもリアルな内容にその悲惨さと恐ろしさが伝わってくるだろう)。 さて、石堂先生が今回の講演のために用意してくださったスライドの一枚が高山の心に深く突き刺さったので、以下に転記する。聴講してくれた4C学生のみなさんの心にもきっと響いたのではないだろうか? 流浪と迫害の人々 ユダヤ人とイスラエルから学んだこと 1) 不条理はあると知る:What you have to do, you have to do.* 自分が全部知っているわけではない(否定的だけでなく肯定的な想定外もある) *やらなければならないことは、やらなければならない 2) 人の知らない苦難はない。これもいつか終わる(This too shall pass)。 3) 命は神の創造であり、自分だけのものではない 一人一人に必ずある使命 「必要な時に、必要な場所に、必要な人がいた」バール・ショーさん 自分に特別に与えられている使命を果たすことこそ生きている意味 社会・世界の“祝福”のために自分は何できるのかという視点 みなさんに与えられた使命はなんでしょうか?私(高山)果たせているだろうか?  ヒト以外の動物が言葉を話すのか? わたしには中3になる息子がいる。息子が使用していた1年生の国語の教科書をパラパラとめくっていたら、興味深いタイトルが目に入った。「言葉」をもつ鳥、シジュウカラである。著者は、鈴木俊貴先生(動物言語学者、ここでいう動物にはヒトは含まれない)。何やて? 鳥が言葉を話す??? そんなわけないやろ!と終始懐疑的思いで読んでみた。内容の一例をあげると、仲間に蛇が来たことをシジュカラは「ジャージャー」と表現する。著者は「ジャージャー」が単なるパニックに応じた鳥の鳴き声(音)ではないことを、巧妙な繰り返し実験により実証したことを記述している。一連の研究はすでに権威ある学会や論文誌で公表されているし、一般向けの書籍(タイトル:僕には鳥の言葉がわかる、 出版社:小学館)にわかりやすくまとめられている(早速、購入して読ませていただいた)。権威ある雑誌(Nature!)に掲載されているとはいっても、それでもわたしには納得がいかない! そこで言語学者は、そもそも何をもって言葉を話すと定義しているのかについて知りたくなった。そうしたら、なんとタイムリーに、興味深い本が出版されていた。「言語の本質 ことばはどう生まれ、進化したか」 今井むつみ、秋田喜美共著、中公新書 なる書籍である。著者らは、この本の中で、オノマトペ(この文章中にあるパラパラが事例)というヒトの言葉に着目し、人の言葉とは何かについて見事に論説している。言語の十大原則を提起し、オノマトペはそれらの原則を満たしているのかという命題に対し、著者らの長年の研究成果に基づいて実証している。そして最後の章に至って「人と動物を分かつものとは」という人類究極の問題に挑んでいる!・・・・・ わたしの結論は、動物(ヒトを除く)が言葉を話すという主張に対して、そのまま受け入れるか受け入れないかは、「言語の十大原則」に照らして、その一部でも満たすならば言葉を話すとするのか、すべてを満たすならば話すとする。この違いになるのではないだろうか? そもそも鈴木先生はシジュカラがヒトの言葉を話すとはいってないのである。ぜひ2つの書物を読んで考えてほしい。 希望をもとう!目標をもとう! 先日、担任クラスでアンケートをとった。4年生からのコース選択(生物工学 or 材料工学)の事前希望調査をとることが主な目的であったが、ついでにと思い、あなたの今の希望(目標)は何でしょうか?と問うてみたところ、ほとんどの学生さんが白紙(無回答)であった。マジですか?と考えさせられた。 以前、担任をするにあたり、3Cの諸君に“3人のレンガ職人”の話をしたことがある(この隔月日記にも書いてありますのでさか上って読んでみてください)。この話は、同じ仕事をしていても、その考え方の違いで、仕事に対するモチベーションが全くかわるということをいっている。明確な目標(自分は盲目的に壁をつくっているのではなく、歴史に残る教会を造っているという喜び!)をもった方が、がぜん仕事のやりがいがあるということである。 一つ前の日記で取り上げた“宙わたる教室”の小説の中に登場する生徒たちもまた、火星のクレーターを再現するという目標をもったことで別人のように変へられていく。 ぜひ目標を見出してほしい。この世に生まれてきたのは、必ず何かの役割を与えられているからなのです。だから、今はわからなくてもあきらめることなくたたき続けて欲しい。そうすれば必ず希望のドアは開くから。 “宙わたる教室” 小説! この小説、まだ体験してないなら、ぜひ! 私は、今年10月から始まったNHKで放送されている窪田正孝が主演を演じたドラマ“宙(そら)わたる教室”を楽しんで視聴してきた。このドラマは、伊予原新さんという作家(惑星地球科学を専攻されたほんものの専門家)が書かかれた小説に基づいている(宙わたる教室 文藝春秋出版)。 ドラマは、指導教員を演じる窪田正孝が、定時制高校にサイエンスクラブを発足し、様々なバックグラウンドを持った生徒が集い、それぞれの生徒が持つ才能(秘められた賜物)を用いながら、力を合わせて
“火星をつくる=クレーターを再現する!”という目標に挑み、最後に学会で成果を発表するに至るまでのプロセスを見事に描いている。 ストーリーの随所にでてくる名ゼリフは、“格言”といってもよく、それが出るごとに強く心揺さぶられ、わたしは涙なくして読めなかったくらいだ(ぜひ小説を読んで共感してほしい!あーこのセリフだなと皆さんも思ってくれることでしょう)。 この小説は、実際にあった出来事を巧妙にアレンジしてストーリーに織り込んである。そのためフィクションでありながら、現実にあったことのように読者に訴えかけてくる。ぜひ一読を薦める。 教員生活最後の研修旅行! 11月11日(月)から14日(木)にかけて3泊4日で3年生物質工学科の研修旅行を引率した。高専に着任して、これで5回目の引率であった。旅行先は東京方面という事で、今回の実習見学先はJAXA、KEK〈高エネルギー加速器機構〉、そして三菱ケミカルの3か所であった。JAXAでは、国際宇宙ステーションのきぼうの管制室をガラス越しに見学することができた。 KEKではスケジュールの関係でわずかの滞在時間であったが、加速器の説明と量子ビームを用いた研究の一部を担当の方から説明いただいた。三菱ケミカル鹿島工場は、日本最大級の化学コンビナート工場であり、工場内をバスで一巡した。要所にて下車し、日本一の高さを誇る煙突と、エチレン生産を行っている設備(柱と複雑なパイプの集合体!)はあまりの大きさに圧巻であった。 2日午後は東京台場、3日目はディズニーリゾート(シーまたはランドのどちらか選択)で丸一日、自由行動をみんなで楽しんだ。わたしが選択したシーの方は、平日であるにも関わらず想像をこえた人込みで、どのアトラクションも長蛇の長時間待ちであり、とても並んで待つ気にはならなかった。結局、わたしが体験できたのは、いずれも待ち時間が30分程度であった水上ボートとモノレールの2つのみで、他の時間は家族へのお土産購入にいそしんだ。 最終日解散後は、個人的に上野の科学博物館を訪れた。充実した展示物に驚かされるとともに、こうした点では東京の子供たちは恵まれた環境にあるなと感じた(遠足で来館した児童たちが眼を輝かせて見学している)。今度は、息子をぜひ連れてきてやりたいと思った。 今回の旅行も大きな事故もなく、無事引率の役割を終えることができた。3泊4日の研修旅行を振り返り、これが教員生活で最後の引率になると思うと、なんとも感慨深い思いになった。  筑波 JAXAにて集合写真 ロバート・オッペンハイマー パート2 映画をきっかけにロバート・オッペンハイマーという人物をもう少し知りたくなった。前回の日記では、少し否定的にオッペンハイマーのことを書いてしまったが、いささか自分が浅はかであった。藤永茂先生が書かれたオッペンハイマーについての書籍*がある。もともとは1996年に初版が刊行されていたようだが、2021年に文庫本が出され、オッペンハイマーの関連書でよいものがないかと書店で物色していたところ私の眼に偶然とまった(極めてラッキーだった!)。なぜラッキーだったかというと、藤永先生が多くの正確な資料(情報)に基づきながら、オッペンハイマーという人物を評価されているからだ。 もし、いずれこの映画のDVDをみる機会があるなら、観る前にぜひこの本を読んでおくことを薦める。多くの登場人物、ロスアラモスでの原爆開発プロセス、原爆投下後のオッペンハイマー裁判と水爆開発への道のりをスムースに理解でき、正しい視点からオッペンハイマーをみることができると確信する(ただし、たとえノンフィクション映画であっても、全てが事実であるとは言えず監督の主観がはいりうるものだということに注意しなければならない)。 ところで、この本を一読して私が最終的に得た結論がある。それは、私がオッペンハイマーの原爆開発の関与について、その善悪を評価することなんて到底できないということであった。 *ロバート・オッペンハイマー 愚者としての科学者 ちくま学芸文庫 母と祇園祭 今回は私の個人的な想いを書かせていただくことに何卒ご容赦を。 先日、長い間ベッド生活を余儀なくされていた母が82歳でなくなった。まだ10年はいきるでーといっていたのがまるでウソのようだ。ただ要介護であり、人の世話を受けないともはやどうにもならない身であった。最後の数か月は、いくつかの病気を併発し、入院を余儀なくされ、ほどなく口からの飲食は全くできないようになり、CVによる延命が続いた。人間とはなんだろう?生きているとはどういうことなのだろうと何度も考えさせられた。この3か月は相当に苦しかったと思う。意識のまだあるときに、出町ふたばの豆大福が食べたいといっていた。とにかく甘党であんこ系が大好物であった。晩年の母とは口論が絶えなかったが、最後に食べさせてあげたかった。ようやく苦しみも悲しみもない場所で、先に逝った父と出会い、今は平安と喜びの中にあると思う。母といえば思い出すのは、第一に、子供の頃によくつくってくれた食べ物のこと。寿司といえば“いなり寿司”、蕎麦といえば “にしん蕎麦”、卵といえば“だし巻き卵”。そして極めつけは“鯛の煮つけ”! そして・・・・どれももう食べることはできない。ここ2、3日暑い日が続いている。晩年の母は、とにかく寂しがり屋になり、故郷を懐かしんだ。時折、涙を浮かべ帰りたいとつぶやいた。遠い昔、幾度か家族で廻った山鉾巡り。コンチキチンのあの季節がやってくる。 目標をもとう! 皆さんは「三人のレンガ職人」のお話しを聞いたことがあるでしょうか?こんなお話しです。建築現場で同じ仕事をしている3人の職人に見物人が問いかける。“あなたは何をしているのですか?”と。1人目の職人は”レンガを積んでいる“と答えた。2人目は”壁を創っている“と答えた。三人目は”神様を讃えるための大聖堂をつくっている!“と答えた。さて、あなたは、この3人の中で誰が自分の仕事にやりがいをもって取り組んでいると考えますか?皆さんは日々学校にきて学んでいる。それは何のため?考えてみて欲しい。 ロバート・オッペンハイマー オッペンハイマーという映画を五月の連休に観た。アメリカでは絶賛された映画であるが日本人にはいまひとつであったように思う(私の知人は上映があったことさえ知らなかった)。この映画に対するわたしの感想はというと、やはりやるせない気持ち(原爆投下を肯定している)が残った。もちろん製作者からすれば映画の主題は別にあるというところだろう。 オッペンハイマーの自著、「原子力は誰のものか」と題し中公文庫から翻訳本が出版されている。私の国語力ではいささか難解な言い回しが多く、内容を完全に理解できたかどうかというとほぼ自信がない。内容はさておき、この本で私が違和感を覚えたのは、オッペンハイマーが核分裂生成物による人体への悪影響について、どこにも触れられていないという点である。広島、長崎両原爆投下後の被爆者の惨状や後遺症について、オッペンハイマーは知らなかったのであろうか?それともオッペンハイマーは、意図的に触れなかったのであろうか(あるいは戦後の冷戦時代という背景から政治的に触れることができない状況にあった)?オッペンハイマーは戦後、日本を訪問しているし、オッペンハイマーが原爆開発のリーダーとして活躍した時代は、1953年にワトソンとクリックによりDNAの構造の謎が解け、分子生物学の開花期とも重なっている。科学者であったオッペンハイマーも放射線や放射能の人体への影響についての知見を少なからず持っていたはずである。不思議でならない。オッペンハイマーは1965年に咽頭がんの診断を受け1967年治療の甲斐なく62歳でなくなっている。 モラトリアム期間! 6回目の担任をスタートして1か月半になりました。この間、担任による個人面談という事で2/3の学生さんとの面談を終えました(5月中に終了予定です)。私と学生とは40以上の年齢の開きがあるだけにお互いを分かり合うためには今少し時間がかかるでしょう(顔と名前を一致させることも結構苦労!)。高専の担任は15歳から22歳という多感な時期にある学生を指導しなくてはならない。一方で学生の方は、在学中に成人年齢18歳(今年度中に)になり、社会的義務と責任を問われるようになる。ところで、タイトルに掲げたモラトリアムという用語は、E. H. Eriksonが「心理学的モラトリアム」として用い定着させた。12~22歳までの期間を「モラトリアム期間」と言うが、解せば「大人になるための準備期間」という意味である。わたしは、これより3年生から5年生(18歳から20歳)までの3年間を担当する。担任の荷は確かに重いのだが、学生の成長する姿をまじかで見て感じることができるのは何よりの報酬である。 新入生歓迎会開催! 今年も恒例の新入生歓迎会が4月10日(水)に開催された。今年度から採用の新ブレザーに身を包んだ一年生の姿は輝いていた。これからはじまる高専5年間、勉学はもちろんながら、クラブ活動やさまざまな学校行事も大いに楽しんでいってもらいたい。 さて、昨今の世の中は、なにかと失敗を批判する(きらう)傾向にあるように思う。しかしここにいる皆さんは、失敗することを恐れないで欲しい。入学にあたり、次の2人の著名人の言葉を皆さんに贈ります。 “本当の失敗とは、失敗から何も学ばない事である” ヘンリー フォード “失敗したことのない人間というのは挑戦した事のない人間である” アルバート アインシュタイン 2024年7月に新紙幣が発行される。北里柴三郎は千円札の肖像画として登場する。ところで、高山は北里という苗字の読みは、てっきり”きたざと“だと思っていたが、”きたさと“が主流のようである。さて、北里柴三郎といえば、日本の病原微生物学の父であり、多くの名だたる後継者(志賀潔、秦佐八郎、野口英世ら)を輩出している。北里はドイツのコッホ(炭疽菌、結核菌、コレラ菌などの発見者)の下で学び(在留中に破傷風菌の純培養に成功!)、最もコッホに認められた存在でもある。彼の業績を上げれば枚挙にいとまがないが、その一つはペスト菌の発見であろう。ペストは黒死病とも呼ばれ、人類史上何度もパンデミックを起こし多くの人々がその犠牲になってきた。北里は明治27年に香港で蔓延したペストの調査に自ら赴き、そこでペスト菌の発見(コッホの4原則を実証)にいたるのである。ただどういうわけなのか北里はペスト菌のグラム染色判定を陽性であるとして誤ってしまう(陰性であった)。ほぼ同時期に発見を競いあっていたフランスのエルサンは陰性と判定し、紆余曲折の結果、このときエルサンが第一発見者とされた。ただし北里の単離した菌は、間違いなくペスト菌であるということは、フランスのパスツール研究所で確かめられている。紆余曲折の結果、ペスト菌はキタサト・エルサン菌と呼ばれるようになったが、現在はエルシニア・ペスティスと改名されており、北里の面影はまったくなくなってしまった。 北里柴三郎の座右の銘の一つに「終始一貫」がある。北里の研究精神に深く通じるものがある。(北里柴三郎 感染症と戦いつづけた男,上野明博,青土社 の一読を薦める。) 担任やります! 4月から3年物質工学科の担任を拝命しました。担任をするのは、これで5回目(5学年から引きいだ担任をカウントにいれるならば6回目!!)になります。年齢的に、なんぼなんでも担任をやるには体力的に無理があるのではないかと躊躇しましたが、最後のチャンスと考えお引き受けしました。17歳(3年生)というと、Z世代とよばれる年代に相当するのでしょうか?ちなみにわたしの年代は、バブル世代とか新人類とかいわれました(どうしてそういったのか調べてみてください)。これから担任をする中で、世代ギャップに悩まされるかもしれませんが、それもまた楽しみの一つです。担任をするにあたり、クラスの皆さんにこれから3年間で養って欲しいこと。それが、“自助の精神”です。自ら学び努力する事とても大事なことです。お互いアップデートしていきましょう。3年間よろしくお願いします。 あんかけうどんと母の記憶 ノンシュガー甘味料としておなじみのアスパルテーム!低カロリーでありながら強い甘みを持つ。わたしは、マクドはダイエットコーク派だ。アスパルテームとは、L-フェニルアラニンメチルエステルとL-アスパラギン酸がペプチド結合してできたジペプチド化合物である(生化学I)。ところで、アスパルテームは、低カロリーであって砂糖に勝る甘い物質を作ろうとして開発されたものではない。アメリカの製薬会社の研究員だったシュラッターという人物により抗腫瘍薬の合成の副産物として意図せず生みだされたものである。そして偶然が重なり、無意識にアスパルテームが付着した指をシュラッターがなめてしまい、その甘さに気づいたのである。通常なら、化学者として注意不足もいいところで、万が一、アスパルテームが強い毒性を持つものであったら?シュラッターはその場でイチコロ(天国いき!)だったかもしれない。さて、ここで“?”としたのには理由がある。ご存知のように、アスパルテームは、すでに多くの食品に低カロリー甘味料として添加されてきている。それとともにその毒性、特に「発がん性」について議論が巻き起こり世間を騒がせ続けている。この問題に対して、国際がん研究機関(IARC)は、このアスパルテームをグループ2Bに分類している。グループ2Bというのは、「ヒトに対して発がん性がある可能性がある」という評価である。この評価に皆さんはどう思うだろうか?これは大変だ!今をもって、アスパルテーム含有食品は一切口にしません!と切りかえるだろうか?もちろんそれも個人の自由だが、おちついてみると、2Bに同じく該当する他の例として、わらびや漬物がある(結構食べるよね!)。そして、もう一つ重要な判断指標となるのが、許容一日摂取量(ADI:一生毎日摂取したとして健康に悪影響を及ぼさない1日あたりの摂取量である)。日本でのアスパルテームのADI値は、40ミリグラム/体重1kgとされている。毎日かかさず、清涼飲料缶を何十本も飲み干すつわものなら要注意かもしれない。ただ世間にはさまざまな化学物質が満ち溢れており、食品添加物もリストアップすれば枚挙にいとまがない。アスパルテームの発がん性にどこまで神経をとがらせる必要があるのか議論は続く。 カタツムリ粘液接着剤! カタツムリのねばねば成分(エピフラム)にヒントを得た接着剤が米国の研究者によって開発されている。YouTubeの画像*で、男性が開発された接着剤を用いて、ぶら下がっている様子をとった動画が閲覧できる。いつも思うが、物質工学科の“ものづくり”というのは、こうしたことだと思う。分子レベルでの材料開発の醍醐味を一人でも多くのみなさんに伝えていきたい。https://www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.1818534116
リン資源問題 レアメタルやレアアース問題と日本はほぼ輸入に頼って、この先どうなることかと悩ましいところですよね。そういうニュースで頻繁に話題になっている元素はともかく、ここ十年來問題になってきているのが、リンの枯渇問題である。リンというと、思い浮かぶのは肥料ですよね。つまり、リンの不足は食料生産問題に直結してくるのです。また、リンは半導体などの工業製品にも使用されているのです。リンなんて、鳥の糞(グアノ)に大量にあるやんけ!と思ったら大間違いで、いまや世界のグアノはほぼ採掘されつくされて、限定された国と地域でしか取れないリン鉱石に依存しているのです(そしてその質が落ちてきていることもさりながら、鉱石からリンを抽出する際にカドミウムをはじめとした大量の有害物質が生み出される!)。リンは私たちの生存に必須であることから、日本はリン枯渇問題に真剣に備えておく必要があるのです。都市鉱山からのレアメタル回収技術にあるように、リンも下水処理場や畜産廃棄物、はたまた製鋼スラグからの回収が今、真剣に取り組まれているようです。 なんでも名前って意味あるんですよ! コロナワクチンで有名なModerna(モデルナ)社の社名はmodified と RNAからの造語である。どうでもよいが、わたしの名前の“勝己”は、両親が初めに“克己”(論語が語源)とつけようとしたが、近所のとある有名な神社(全国的にも由緒ある神社)にいってみてもらったところ、字画がどうのこうのということで“勝己”にかわったそうだ。わたしの場合、読みは“かつみ”なのですが、“かつき”が本来の読み方なのです! ところで、RNAを人体に注入すると免疫システムにより異物と認識され排除されてしまいます。これを抑制するためにカリコ博士とワイスマン博士が、RNAをシュードウリジン修飾することで解決したのです。すごい執念ですよね。ただ実用的ワクチンとして用いるには、他にもクリアしなければならない多くの課題があり、脂質ナノ粒子に修飾したmRNAを封入したことも成功のカギとなったのです。 マルチバース(多元宇宙)理論! 今年も例年のごとく自宅玄関先で育てていたカブト虫の幼虫が6月下旬に大量羽化し、つい最近まで20匹近くを飼育していたが、狭い空間に閉じ込めておくのも忍びなく感じ、自然にかえしてやった。みんな元気に近くの足羽山目指してとびたっていった。さて、話かわっていつものように書籍の紹介をさせていただく。 サンマーク社から出版された「すらすら読める新訳フランクリン自伝」という書籍を読んだ。雷が電気であることを証明するため凧の実験を行い、アメリカ100ドル紙幣の肖像画になっている人物だということだけは知っていたが、彼の生涯や考えがどういうものだったのかということは全く知らなかった。“すらすらよめる”とあるだけあって、ちょっと夜更かしして一晩で読めた。特に印象に残ったのは、彼が掲げた13の徳目である!ベンジャミンが生涯にわたって獲得していった“徳”なのだから、もちろんどれも必須なのだが、13番目にある“謙虚”は、ベンジャミンが最後に掲げた“徳”だけあって、わたしの心にもずっしりと響いた。わたしも日々“謙遜”でありたいと心がけている(願っている)のだが、どうにもこうにもこれが実にならないでいる!!あらためて言い聞かせられた気がした。 エリック・バーン名言 「過去と他人は変えられない。あなたが変えられるのは自分と未来だ」
3月17日卒業式が挙行された。3年にわたるコロナの影響もようやく終息を迎えようとしている。日本もいよいよアフターコロナ(それともwithコロナというべきか?)の時代に入ろうとしている。みなさんはそんな中での船出となる。さて、万事がうまいこといっているときは人生バラ色だろうが、これからも長い人生いいことばかりではない!苦難を通るときもあるだろう。そんなとき、「なんでこんな災いが自分にふってくるんだ!」「なんで自分だけがこんな思いをしなければならないんだ」と悲観しないで欲しい。そんなときは、「いま受けている苦難は自分の人生にどんな意味があるのだろうか?」「この苦難を通して自分は何を学ぶことができるだろうか?」と考えて欲しい。艱難の先には必ず希望があると信じて欲しい。
遅まきながらChatGPTを試してみた。「生命とは何か」とAIに問うてみた。回答(あえて解答としないでおきたい)は、「生命とは、生物が持つ特徴的な性質やプロセスの総体であり、生命現象とも呼ばれます。生命の特徴的な性質には、自己増殖・自己維持・自己修復などがあります。生命現象には、代謝・成長・発生・遺伝などが含まれます。・・・・」ときたー。なかなか優秀じゃないか!これを、試しにそのままペーストしてGoogle翻訳にかけると(最初から英語でGPTに問いかければよいのですが)、「Life is the totality of characteristic properties and processes of
living things, and is also called a biological phenomenon. Characteristic
properties of life include self-proliferation, self-maintenance, and
self-repair. Life phenomena include metabolism, growth, development, and
heredity.」とでる。もうお気づきだと思うが、そう!うまく使いこなせば、日本語も英語のレポートもAIが作ってくれる時代となりつつある。教員も予想外の学生の質問がでても、あたりさわりない受け答えができる。びっくりだ。さて本当にこれでよいのだろうか?ChatGPTの回答は、常人では網羅できない膨大なデータベースに基づいて生み出されるものなのだろうが、もちろん正しくない情報が含まれてしまう可能性はある。その誤りを見極める能力が使用者側あることが大前提である。本来は、自分で必要な情報を収集でき、正しいものであるかを吟味でき、取得した知識を知恵へと昇華させていく能力を養うことが大切なのである。便利なものを使うなというわけではないが、学生もさることながら、教育者はこのことをしっかり認識し、学生を教え導かねばならない。だから学び続けなければならない。 話はかわるが、AIが不特定多数の膨大なデータベースを駆使して、巧妙な演説をしたとして、人は果たしてその演説に心打たれるだろうか?魂にふれる演説とは、その人の人生の実体験に基づいたものから生み出されるものではないのだろうか?AIの作った人工物に人が惑わされることがあってはならない。古いといわれてもいい!わたしはそう思うし、AIは活用すべきだが、AIは人ではないし、人にはなれない。皆さんはいかが考えるだろうか?
専攻科発表報告会 1月24、25日と両日に専攻科生による研究報告会が実施された。大雪に見舞われ、実施が危ぶまれたが、Teamsも併用してなんとか開催できた。発表を聞いていて思ったのは、専攻科生が本科(5年生卒研発表)の時に比べて自信に満ち溢れ、教員からの質問にも決して臆さず、明確に受け答えできるまでに成長していたことになんだか嬉しく思った。1年生については、来年にむけさらなる飛躍が楽しみである。 ハンス・クリスティアン・エルステッド
ファラデーとヘンリーは電磁誘導の発見者である。この発見からおよそ半世紀後に、交流発電機の開発者であるニコラ・テスラとジョージ・ウエスティングハウスは交流送電システムを実用化し町に明かりを灯した(なお直流送電システムの開発者であるエジソンとの戦いの映画(エジソンズ・ゲーム)もあるので鑑賞を薦める)。相対性理論で有名なアインシュタインは光電効果の理論(論文:光の発生と変換に関する1つの発見的な見地について:1905年)を発表し、この業績によりノーベル賞を受賞した。金属に光があたると表面から電子が飛び出してくる現象に対する理論である(光は粒子でもある)。これは、太陽電池の原理となり、時を経て、今や再生可能エネルギーの代表格である。基礎研究の重要性を示すいい例ですね。
「柔らかな答えは憤りを静める。しかし激しいことばは怒りを引き起こす。」と聖書の箴言15-1にある。様々な場面で、自分が知らぬ間に頑なになっていっているのにふと気づかされることがある。今年はこの言葉をしっかり胸に秘めていきたいと思う。 シュレーデインガー名語録! The task is, not so much to see what no
one has seen yet; but to think what nobody has thought yet, about what
everybody sees. というのがある。 2023年最初のお薦め本
クリックケミストリー(Click Chemistry)&生体直行化学でノーベル化学賞! キャロライン・ベルトッツイ、モルテン・メルダール、バリー・シャープレスの3人の博士は、 2022年度のノーベル化学賞受賞者である。シャープレス博士に至っては、2回目の受賞であり、1回目は日本の野依博士との不斉触媒開発における共同受賞である。従来の化学合成は多段階の行程を要したり、多くの副生成物が生じたり、高温高圧といった過酷な条件を必要とする場合が多かったりするものなのであるが、こうした問題をクリアした合成法がクリックケミストリーである。車のシートベルトを“カチッ”とはめるように、分子と分子をつなぎ合わせる方法である。代表例としては、アルキンとアジドの結合反応がある。両者は銅触媒の存在下において、水溶媒中、室温で、余計な副反応物も生じることなく進行させることができる。この研究の先駆けとして貢献したのがメルダール博士とシャープレス博士であり、今や新素材や新薬の開発にどんどん導入されている。そして、このクリックケミストリーの技術を、生命科学領域まで拡大させたのがベルトッツイ博士である。細胞の表面にアジドを末端に持った糖鎖を発現させ、クリックケミストリーの反応を利用して、緑色蛍光分子で表面を修飾した研究報告は見事としかいいようがない(Proc. Natl. Acad. Sci USA(2007)104, 16793-16797)。これこそ化学と生物に基盤を置く物質工学科の醍醐味といっても過言ではないだろう!
11月8日は442年ぶりの一大天体イベント(皆既月食と天王星食のダブルイベントなり)だった。息子に無理やり外に出されて、一緒に夜空を眺めた(眺め続けた)。少しずつ月がかけはじめついに皆既月食となった。そのタイミングで、今度は小さな天王星が月に隠れるというものだったが、そこのところは肉眼では観測不可能だった(根本的に家の周辺が夜霧に包まれ月がどこにあるのかわからなくなってしまった!)。そこで天王星食の観測はというと?実は、Web配信画像をみて“ずる”をした。大きなほっぺの後ろに、小さなゴマが隠れていくそんな感じだねと息子と語り合った。望遠鏡購入したいなという誘惑が私を襲っている。
マリモはアオサ藻綱シオグサ目に属する藻類である。北海道の阿寒湖に生息している国の特別天然記念物である。このマリモが球化するのになんと微生物が一役かっていることがわかっている。ところで、球化する藻としては、阿寒湖のマリモの巨大さには及ばないが他の地域でも見つかっているようで、例えば奥飛騨丸藻(マルモ)という商品が売られているようだ。実はわたしも福井県の若狭湾で取得した小さいながらも球化する藻を見つけた。現在、これをなにかに使えないか模索中なのである。 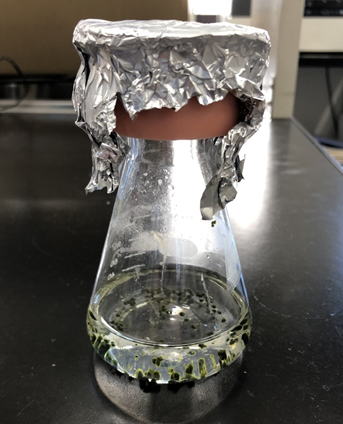 マリモに遠く及ばない数ミリ程度の球状ですが! もしもっぺんやり直せるなら物理か? 本棚を整理していたら、10年くらい前に読んだ本が片隅からでてきた。多田将先生が書かれた イースト・プレス出版からの「すごい実験」である。茨木県の東海村にあるJ-PARCという名称のついている高エネルギー加速器を紹介した本である。当時、この本を手に取ったとき、著者である多田先生の風貌に高山は衝撃を受けた記憶がある。今になってもそのヘアースタイルを維持されているのか興味あるところである。この本はJ-PARKの紹介はもちろんなのだが、素粒子物理学のこれまでの流れがわかりやすく書かれていてありがたい。サブタイトルに“高校生にもわかる素粒子物理の最前線”とあるが、出版から10年以上経過しているので、その後の進展は反映されていないがそれでも一読をお勧めする。実は、高山は中学生の時は、将来は物理をやりたいと思っていた。叔父が“核融合”に関わる研究をしていたので、その面白さを情熱的に語ってくれたことが大きかったと思う。ところが結果は今ある通りで、高専の物質工学科で”微生物“の研究をやっている。目に見えないものを対象としていることに違いはないが、大きさの桁が違うし、アプローチの方法も異なる。人生の岐路での選択とは不思議なものであり、その時興味があったからというだけですまないものだ。ただ、もしもう一回やり直せるとしたらどうする?と聞かれたら・・・・・。それでも私は物理ではなく生物をとると思う。理由は?と聞かれても、それは自分の性格に合っていると感じるとしか言いようがない。 サーバント リーダーシップ! 先日、高山が指導させていただいた専攻科卒業生が共同研究のことで訪ねてきた。自身が取り組んでいる課題について資料を用いて説明してくれたのだが、そのプレゼンの資料が実によくできていた。卒業してまだ数年での、著しい成長に自分の事のように嬉かった。 〇 サーバント リーダーシップ入門,池田守男,金井壽宏著,かんき出版 です。 サーバント・・・・なんだそれ!と思われる人は多いでしょう。 サーバント・リーダーシップの定義は、
中学生のみなさんは高専受験にあたり、どの学科を選択すべきか考えるときに、物質工学科(化学)って具体的にどんな分野なの?と疑問に思うことでしょう。そんな時に、一読をお勧めしたいのが次の本である。ぜひとも参考にしていただけたらと思う。 〇 化学で「透明人間」になれますか?人類の夢をかなえる最新研究15、佐藤健太郎、光文社新書 五山の送り火 今年は3年ぶりに京都では五山の送り火が再開となった。鴨川のほとりで、幼いころに祖母に、なぜ東山(如意ケ嶽)は山火事にならないのと聞いたのが、ついこの間の出来事に思えてならない。火床と呼ばれるものを使っているわけで、直接、山の木を燃やしているわけではないということをその時知った。その祖母は他界して久しい。生とはなんなのか?人がなくなる度に考えさせられる。 植物と昆虫の学び 夏休みに息子と親子植物教室「植物と昆虫のふしぎ」に参加した。講師は東京大学の川北篤先生だった。講義と実習の2時間弱の教室だったが、特に印象に残った内容が、植物の「自切(じせつ)」という現象だった。植物の葉が、病原菌に感染したときに、その感染した部分を自ら切り落とす現象だという。とかげに代表される尻尾切りは知っていたが、なんと植物にもそのような仕組みがあろうなどとはわたしには衝撃であった(もちろん主題である花の色と昆虫の関係のお話しも大変興味深かった)。小学生対象の勉強会であったが、知らない事ばかりで、ますます自然が好きになった。それから、あのイチョウの精子を発見した平瀬作五郎先生が福井県出身であることを教わった。知らない事ばかりで、お恥ずかしい限りである。平瀬作五郎先生は、植物学者であり、画家(用器画法)
でもあったということで、本当に昔の偉人は多才であったのだと痛感した。 合成生物学! 「自分で作れないものを、私は理解していない」とは、リチャード・ファイマンの言葉である。人類は、偉大な生物学者達の努力の蓄積により、生物のもつ素晴らしい“しくみ”を知ることができます。今のところ、どんな偉大な科学者が集まっても、生命そのものを生み出すことはできませんが、21世紀になって少し様子が変わってきたようです。合成生物学の登場です。 合成生物学の目標の一つは、科学者が設計した通りの性質を持った人工生物を生み出すことにあるといっても過言ではありません。合成生物学の原動力は、ゲノム計画により21世紀初頭に、ヒトDNAの30億塩基が明らかになったこと(PCR、塩基配列解析法など遺伝子組変え関連技術の進歩が支えた)、また長鎖DNA合成技術とCRISPER-Cas9に代表されるゲノム編集技術等が近年確立されたことにあります。そして、DNAを読むだけではなく、いよいよヒトのDNAもその気になれば近い将来合成可能であり(アメリカでは関係の研究プロジェクトが進行している!)、加えてコンピュータを駆使して科学者が意図する形質を持つように遺伝情報設計することも可能なのです。 ところで、この段階までであれば、DNA分子の合成ということになりますが、合成したDNAをヒトの卵子に導入したら・・・・。と考えると、合成生物学の究極的な進展が導くであろう光と影(闇?)が見えてくる。私自身がこの研究に携わることはないが、こうした研究の原理やその波及効果は想像できる。物質工学科で5年間学んだ学生であれば、もちろん理解できるようになる。21世紀は生命科学がますます私たちの生活に利用される時代となることは間違いなさそうだ。とりわけ合成生物学は、人間社会を劇的に変えることになるだろう。ただし、その発展がもたらす結果が、いいこと尽くしとなるかどうかは疑わしい。扱いを間違えば、後に戻れない悲惨な結果を招くのではないだろうか。どこまでなら研究として認められるのか?決して越えてはならない一線をいったいどこに引くべきなのか?その一線は、何に基づいてきめるのか?これからの21世紀を生きる、ひとりひとりが真剣に考えなければならない問題ではないだろうか? 最後に、話変わりますが、今公開中の映画ジュラシック・ワールドに登場する超巨大バッタ(素朴な疑問:現在の地球大気の21%酸素濃度では生存無理では?)は、T-rexをはじめとするやたら凶暴な恐竜たちよりもずっと恐ろしく感じたのは私だけだろうか?人類の夢の実現であるとか、恐竜と人間の共存は可能であるとする主張には疑問を感じた。一度絶滅した(自然現象)ものを蘇らせることは人間のエゴに思えてならない。(あくまで私見ですのでご容赦ください。) 合成生物学,ジェイミー・A・デイヴィス著,ニュートン新書 バイオビルダー 合成生物学をはじめよう,ナタリー・クルデルら 著,オライリー・ジャパン 師の言葉の重み わたしのこれまでの人生をあらためて振り返ってみると、重要な岐路のところでは、いつもすばらしい師の存在があった。いまでも恩師からいただく言葉は重く、その言葉に涙がこぼれる。そして、その言葉の中にあらためて気づかされることがある。まだまだ自分は未熟だなと反省させられる次第である。人との出会いを皆さんもぜひ大事にして自らの成長に繋げて欲しい。 温暖化問題 何年か前から専攻科で「地球環境」という教科を担当している。私自身は、専門家でもなんでもないので、自分自身も毎年講義の都度、スポットをあてる環境問題に関する情報を集め、学びながら教壇にたっている。さて、地球温暖化問題がクローズアップされて久しい。この問題が指摘された当初のころから、科学者間で賛否にわかれ激しく議論されてきた。特に二酸化炭素の大気濃度の増加が原因であるとすることに対する議論は、いまだに続いているように思う。さまざまな情報を簡単にインターネット経由で入手できる時代なのだから、他者の意見を鵜のみにするのではなく、まず自分で調べて吟味することが大切だと思うが、やはり最も信頼できるのはIPCCの報告書ではないかと私は思っている。IPCCが、二酸化炭素が温暖化の大きな一因であるとする根拠が気候モデルを用いたシュミレーションである。 最近知ったのですがみなさんは「好適環境水」なるものをご存じでしょうか?岡山理科大の山本俊政先生という方が、長年の研究の成果により、さまざまな淡水魚、海水魚そしてエビなどを養殖できる第三の水を開発され、山間部における魚の養殖を可能にしたというすぐれものです。カクレクマノミとキンギョが同じ水槽で泳いでいる映像(YouTube)はびっくりです。ナトリウム、カリウム、カルシウムを主成分としているようで、これにpH調整剤やその他の成分を養殖対象によって必要に応じてプラスしたもので、「好適環境水」と山本先生が命名されたもの。既に国内特許も取得されています。この水を使用することの利点の一つに養殖魚の細菌感染問題を回避できることであり、使用後の水(魚の排せつ物により窒素やリンが含まれている)も捨ててしまう(捨てられない)のではなく、畑から取得した微生物で処理するか植物工場用の水(N,Pは植物の成長必須成分)として再利用します。後者の場合、海から遠く離れた山間部で、完全環境制御型の漁業(養殖)と農業(植物工業)を両立できるという事。この研究・技術の概要は、山本先生の書籍「宇宙マグロのすしを食べる」をお読みいただきたい。 山本先生の研究は、いわば化学と生物の両分野に基礎を置かれたものであり、わが物質工学科のアドミッションポリシーの一番目に掲げた「化学と生物の力により人々の健やかな生活に貢献する」にマッチする一例といえるのではないでしょうか。
アクアポリンは細胞膜に埋まっている水チャネルである。水分子のみを選択的に細胞内に取り込む機能を担っています。ピーター・アグレという研究者が発見し、この功績により2003年にノーベル化学賞を受賞しました。そして、どのようにして水分子がアクアポリンを通っていくのかも解明されています。ここまでは純粋なサイエンスの領域といえるでしょう。
最近、本当に悲しいことが多く起こります。こうした時代にこそ、我々を導くリーダーの役割は重要ですね。 “そこで、まず初めに、このことを勧めます。すべての人のために、また王とすべての高い地位にある人たちのために願い、祈り、とりなし、感謝をささげられるようにしなさい。それは、私たちが敬虔に、また、威厳をもって、平安で静かな一生を過ごすためです。”
京都タワー といえば タワー浴場! 京都タワーって世界一高い無鉄骨建築(ギネス認定)だってことご存じでしたでしょうか?モノコック構造といって鉄骨を使用していないのです。飛行機や船と同じ構造ですね。1964年に開業し(私が生まれる2年前!)、赤と白の独特の京都らしいカラー。その丸みを帯びたフォルムは京都駅前のシンボル。その高さ131メートル。実はこの数字は、当時の京都市民の人口と同じ。ところで、この京都タワー地下には大浴場があったのですが、ついに店じまいになったとのこと。実に残念です。子供のころ母親につれられて、ちょくちょくつかりに行ったのがついこの間のようです。2012年に一度リニューアルしていたそうですが、ついに終わってしまったようで、もう一回いっておけばよかったと後悔しています。 MRI検査受けてきました! MRI検査受けたことありますでしょうか?ちくわのような狭い筒のなかに送り込まれて、数十分間、ガチャンガチャンと大ノイズの響き渡る狭い空間にベルトで縛られてじっとさせられます。いまに壊れるんじゃないのか!この音なんとかならんのかと思いますが、技術改良の余地ありやね!といった次元の問題ではなく、物理現象(フレミングの左手の法則によるローレンツ力)につきどうしようもない。さて、このすばらしいMRI装置。誰が開発したのかというと、アイデアはダマディアン、装置として初めて実現したのがローターバー、そして人体撮影における実用レベルにまで押し上げたのがマンスフィールドという研究者なのです。そしてこの偉大な発明に対して、ノーベル賞はローターバーとマンスフィールドとなりました。ちなみにノーベル賞は3人まで受賞できるので、ダマディアンがどうして選ばれなかったのか?という疑問がわくのですが奇妙なお話しですね。 ペニシリンの発見者フレミング! アレクサンダー・フレミングはペニシリンの発見者です。子供のころの話ですが、わたしが風邪をひいて熱をだすと、祖母は真顔で母に、“はよう病院つれてって、注射(ペニシリン)打ってもらってきいや!”とよくいわれていました(効くわけないのですが!効くもんやと信じていました)。
さて、フレミングは実験で用いたブドウ球菌を培養していたシャーレを流しに放置したことで、空中をただよっていたカビがシャーレに入り、カビがつくる物質が細菌の増殖を阻害していることに気づいたのです。そして、このカビがつくる物質が殺菌剤になりうる可能性を1929年に論文で発表したのです。ただし、この発見は、フロリーとチェインが有効成分としてペニシリンを分離・精製するまで、しばらくの間眠ってしまいます。ということで、この偉大なる発見(抗生物質開発の開花)に対するノーベル賞は、めでたくフレミング、フロリ―、チェインの3名に授与されました。このストーリーについて、みなさんはどう思いますか? “なんや。フレミングは、ほったらかしたシャーレからたまたま大当たりを得ただけやんけ” と思ったらそれは大間違いです。彼の鋭い洞察力こそ研究者には必要な素質なんです。フレミングはこのほかに、リゾチームの発見にもよく似たストーリーがあります。細菌培養中に、うかつにもクシャミをしてしまい、彼の鼻汁がシャーレに入り、あとで溶菌が起こっていることを発見したことがきっかけだとか。微生物研究をこよなく愛し、楽しんでいたというフレミング。わたしもフレミングにあやかりたいもんです。 カブト虫が羽化しました! 6月30日早朝。今年もカブト虫、第一号が羽化しました。梅雨明けが早く、猛暑のためか、今年は例年より2週間程度はやいようです。我が家の幼虫飼育箱には30匹程度生育していたはずだから・・・。今年の羽化率は、どの程度になるか楽しみだ。小学6年生になった息子の関心は、少し薄れつつあるのに対し、自分は興味津々、毎朝、様子をチェックしています。この夏もゼリー代半端ないだろうなと思いつつ。 レオンハルト・オイラー オイラーは数学者の王者といわれている大人物です。あの大物理学者のファイマンをもうならせたオイラーの公式(eix = cos x + i sin x)に始まり、オイラーの等式(eiπ + 1= 0)には究極の美しさがあるという!正直、残念ながら、わたしには美しいと感じる感性が備わっていませんが・・・・。実は、最近、時間のある時に、高校の数学を復習しています。ゆったりと、時間に追われることなく、気ままにやってると(かつては試験に追われて強いられていた!)、少しだけなのですが、数学の面白さを感じるようになってきました。いつまで続くやら。 赦し = 心の平安 = 健康 皆さんは日常生活の中で悔しい思いをしたことはありませんか?どう考えても納得できないという込み上げる思いですね。私は数えきれないくらいあります。でもそういう思いをずっと引っ張っていると、不健康になり、いつまでも心に平安が得られないのです。常に思い煩って元気が出ないのです。損ですよね!簡単ではないのですが
“赦し”というのは大きな人生のテーマです。 小説家 三浦綾子100周年ですよ。 今年は三浦綾子さん(クリスチャン作家)生誕100周年にあたる。三浦さんは朝日新聞社の懸賞小説に入選した「氷点」がデビュー作である。三浦さんの作品は80を超え、私はその中の数冊しか読んでいないのですが、現段階でわたしが最も感動した(涙で溢れかえった)のは「塩狩峠」である。まさに究極の愛(アガペー、自己犠牲)が小説のテーマになっている。三浦さんの小説はいずれもキリスト教の教えが土台となっている。この機会にぜひ一読をお薦めする。もう一冊、小説ではないのだが晩年になって出版された「明日のあなたへ」は、三浦綾子さんの回顧録であり、これもクリスチャンとして歩まれた三浦さんの人生観が伝わるものであり、心にずしんと訴えかけるものがあり、“すばらしい”の一言に尽きる。 お薦めの本 今回紹介したいのは、集英社新書から出版されている「原子の力を解放せよ」と、早川書房から出版のカズオ・イシグロ(2017年ノーベル文学賞受賞作家)による「わたしを離さないで」(原題:Never Let Me Go)の2冊である。いずれも映画化されているが、映画はすべてを描き切っていないので書籍をまず読むことを薦める。 前者は第二次大戦下の日本の原子核物理学の権威であった荒勝文策とその学生たちの通称「F研究」に関する実話である。この研究が原子爆弾の開発を真に意図して行われていたものなのか、純粋な原子エネルギー有効利用を目指して行われていたものかは読者の判断によるのだと思う。そして、もう一つ福井高専として知っておいて欲しいのは、この荒勝教授の意志を継がれたのが木村毅一先生であり、最後の赴任地として本校の初代校長をされた方なのである。図書館には木村先生が書かれた「アトムのひとりごと」という書籍があるのでぜひ借りて読んで欲しい。 次に、後者であるが、クローン人間が人権もなく、ただただ臓器ドナーとして利用されつづけるというなんとも恐ろしい(ストーリーの最後まで希望が見えない)お話しなのである。最初わたしにはイシグロ氏がなぜ小説の時代背景を、生命科学が花開いたばかりの20世紀後半あたりに設定したのか不思議に感じた。しかしじっくり読んでいると、むしろノスタルジックな雰囲気がこの分野の発展に隠れている危険性を警鐘するのに効果的に働いていている。21世紀になりiPS細胞,ゲノム編集,遺伝子ドライブといった科学・技術が生まれたことで、今後どんな社会になっていくのだろうかと深く考えさせられる一冊である。人はだれもが少しでも長く生きたいと考える。でも肉体の死は必ず訪れる。 やっと妻と一緒に帰省しました! 本当に久しぶりに妻と息子とともに京都と兵庫にいってきました。 最近、息子が幕末史にはまって いて、ちょうど良かれと思い二条城から壬生界隈を歩いてきました。京都の町をあるいて、思わず母親と一緒に歩いた自分の子供時代と重なりました。あのころは京都の町には、けっこう縦横に市電が走り回っていました。その母親はいまはすっかり腰を痛めて自由がききません。まるたけえびす歌や月はおぼろに東山~と母はよくうたっていました。すこし郷愁にふけりました(すみません)。翌日、伏見の寺田屋まで足を伸ばしました。桜が満開ちかくなってました。3日目は妻の実家に移動し、近所の甲子園で、ちょうど近江と大阪桐蔭の試合を観戦してきました。それにしても若いっていいね。福井高専もいつか甲子園出場できるといいですね。  二条城:将軍の気持ちになって入城!  八木邸: 新選組の屯所として使われた邸宅です。 芹沢鴨が暗殺された場所であり、丁寧なお話しが聞けます! 八木家は、なんと越前朝倉家に繋がるとのこと。家紋をよく見てください。 朝倉遺跡の建物にあるやつと同じなんですよ。びっくりですね。 とても勉強になりました。  これが寺田屋です。ながいこといたのに始めて見学しました。  これが竜馬が襲われた夜にお龍(りょう)さんがはいってたお風呂です。  桜が咲いてました。十石船とのコントラストが映えます。  伏見は京都の酒蔵!ここは月桂冠です。酒造りにかかせない 伏見の地下水(伏水)がとれるのです。この水は鉄分が少なくカリウムと カルシウムを適度に含んでいるのです。伏見にいったら大倉記念館に ぜひ立ち寄ってみてください。  大阪桐蔭半端ないよ。いつの日か福井高専も! ゴルフボールにはなぜ凸凹があるの? ゴルフボールの表面にあるデインプルの役割は、ボールが正確に真っすぐ飛ぶようにすることと、よりよく飛ぶようにするためにある。デインプルがないと、飛距離は半分くらいになるそうだ。 この1月の中旬にわたしは、人生ではじめて長期入院を余儀なくされました。初めの一週間は高熱が続き、一度は、自分はもう死ぬのではないかと思うような状態にまでなりました。 幸い回復することができ、今は療養期間となっています。この入院生活で、私は学んだことがあります。それは、多くの方が、コロナ規制の中で、自身がコロナに罹患しているそうでないにかかわらず、全ての入院患者が家族に会えない状況に置かれているということでした。場合によっては想像もつかない病気との戦いの中で、孤独を強いられ恐怖の中に置かれている方が大勢おられるということでした。 人は病に苦しんでいる時にこそ、より沿ってくれる家族(心を許せる人)が恋しくなるものです。それが叶えられない辛さを、身をもって体験しました。別の病気に罹って、カーテン一枚だけ挟んで、隣のベッドで伏しておられた全く見ず知らずの方のために、私は心からその方の回復を祈ることができたのです。この一時だけのことかもしれないけれど、私がその方の回復のために心から祈れた事。そういう自分に変えてくださった恵みに感謝でした。 今回の入院を通して、〝艱難を喜びとせよ“。という聖書の御言葉を思い出しました。もちろん艱難そのものは喜べない。でもそこを通して得られるもの(変化)が大きいのである。だから喜べなのである。YouTubeで見ることができますが、レーナ・マリアさんというスウェーデンのクリスチャンの方がいます。この方が歌っている〝聖霊にみたされて”という曲(山本さんという方が作詞・作曲)を偶然に聞いたとき、自身の心境にぴったりと重なり、涙で溢れかえりました。 今、こうして生かされていること、それだけで十分感謝であると。皆さんもじっくり自分自身と向かい合って欲しい。人生において心が折れそうになるような、苦難や理不尽なことに襲われることがしばしばあるでしょう。この世は試練や苦難で満ち溢れていて、もう絶望的にしか思えないこともあるでしょう。でもそれは、本当に乗り越えられないような試練だろうか?考えて欲しい。あなたは高価で尊い存在なのだから。 |